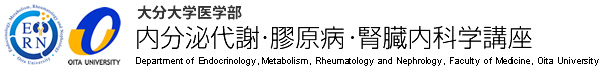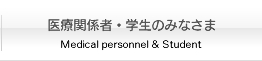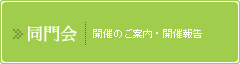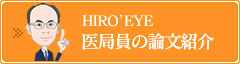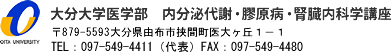ホーム > お知らせ
内分泌糖尿病内科 佐田 健太朗医師(大学院生)が、第94回内分泌学会において、KO roundsでRunners up賞を受賞致しました。おめでとうございます!
佐田健太朗先生(内分泌糖尿病内科) |
日本内分泌学会では、若手臨床内分泌医育成委員会の企画として「KO Rounds」という企画を総会の会期中に行っています。これは、若手医師が持ち時間3分間でスライド1枚を自由に様々なデザインや手法を用いて自分が経験した症例や研究内容をプレゼンテーションする企画です。私が本委員会の委員長として第90回総会(2017年)より企画して始めました。毎年多くの演題応募があり、内分泌症例に対する「目利き」としての視点、「面白さをまとめる」、「うまく伝える」の3つの要素を競う企画です。
過去には、第90回総会(2017年)に内分泌糖尿病内科の岡本将英先生がRunner-Up賞、野口貴昭先生がアイデア賞を受賞しています。今年の総会では、昨年コロナ禍で開催できなかったため、93回総会と94回総会の2年分をまとめてWebにてZoomを用いて行われました。内分泌糖尿病内科の佐田健太朗先生(厚生連鶴見病院)と松田直樹先生(大分赤十字病院)がそれぞれ研修病院で経験した症例発表を応募したところ2名とも第93回総会にて書類選考で選出されました。学会中の最終選考では佐田健太朗先生が「持続血糖測定(CGM)にて無自覚性低血糖を認めたSLC5A2遺伝子変異をともなう家族性腎性糖尿病の1家系」の演題でRunners-Up賞を受賞しました。佐田先生はすでにこの症例をJournal of Diabetic Investigation誌(Clinical and genetic analysis in a family with familial renal glucosuria: Identification of an N101K mutation in the sodium-glucose cotransporter 2 encoded by a solute carrier family 5 member 2 gene. 11:573-577, 2020)に英文論文として発表もしています。
最終選考での発表は3分間ぴったりの発表で、アニメーションを使い、必要以上の情報を含めないことでわかりやすいものでした。何よりも、「それまでの視点とは180°真逆の視点から物事をとらえること(コペルニクス的転回)」を引用して、家族性腎性糖尿は疾患ではなく健康的に無害であると考えられている常識とは異なり、実際には夜間に無自覚性低血糖が連日起きていたことをCGMという新しいデバイスを用いて証明した素晴らしい内容でした。今後、家族性腎性糖尿は「健康被害がない」という一般に受け入れられている内容は正しくないのかもしれず、今後の経過をみる必要を示した貴重な発表でした。
この発表は、佐田先生が厚生連鶴見病院で研修中に、内分泌代謝内科の日高周次部長の指導でまとめたもので、市中病院で研修中に指導医と共に仕上げた点でも大変評価に値するものです。佐田先生は今年の4月から大分大学医学部の大学院博士課程に進学しており、この受賞をモチベーションとして、さらに研究成果を上げることを期待しています。
(柴田洋孝)
<受賞の感想>
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座の佐田 健太朗と申します。この度は、第94回内分泌学会学術総会において、KO roundsでRunners-Up賞を頂くことができ、大変光栄に存じます。
今回、私は「持続血糖測定(CGM)にて無自覚性低血糖を認めたSLC5A2遺伝子変異をともなう家族性腎性糖尿病の1家系」と題して発表させて頂きました。本症例は、大分県厚生連鶴見病院で経験させて頂き、同院糖尿病代謝内科部長の日高周次先生、当科教授の柴田洋孝先生の御指導のもと、Journal of diabetes investigation誌に投稿させて頂いた内容になります。
家族性腎性糖尿(FRG)は持続性の尿糖排泄を認めるにもかかわらず、尿糖陽性以外に特記異常所見がなく、基本的には無症状であり、疾患というより一つの表現型として認識されてきました。論文化にあたっては、FRGにおける新規の遺伝子変異を発見したことを主軸に記載させて頂きました。本症例では、CGM(FreeStyle リブレ Pro)を用いて血糖推移を確認したところ、夜間を中心とした無自覚性低血糖を示唆する所見を認めたため、KO roundsではこの点に着目して発表させて頂きました。FRGは、前述させて頂いた通り無症状で尿糖陽性以外の異常所見に乏しく、入院精査となることは極めて稀なため、外来受診時の血液検査や75gOGTTの結果以外に詳細な血糖推移は確認されていませんでした。近年、技術の進歩によりCGMを用いることで外来でも24時間の詳細な血糖変動を確認することができるようになり、今回の発見につながりました。
今回の症例から、技術の進歩によりこれまで認識できていなかった(技術的に確認できなかった)新たな事実が明らかになると、それ以前の常識が覆る可能性があるということが教訓になりました。このことは、かつてコペルニクスが唱えたものの人々から受け入れられなかった地動説が、現代においては常識となっており、宇宙空間からの地球の映像も見ることができ、誰しもがその事実を実感できることとの繋がりを感じ、「コペルニクス的転回」の説明を踏まえて発表させて頂きました。私たちの周りには、このような新たな発見の種がまだまだたくさんあると思われ、少しでもそれらに気づくことができるよう、今後もリサーチマインドを大切に臨床・研究に従事して参りたいと存じます。
末筆になりますが、今回の発表におきまして手厚い御指導を頂きました日高部長、柴田教授に感謝申し上げます。また、論文執筆に際して御指導・御協力頂きました、近畿大学医学部 内科学教室 内分泌・代謝・糖尿病内科部門 主任教授 池上博司先生、准教授 能宗伸輔先生、四国こどもとおとなの医療センター 小児ゲノム医療研究室長 片島るみ先生、大分大学保健管理センター 加隈哲也先生、そして鶴見病院のスタッフの方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
(佐田健太朗)