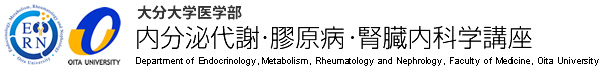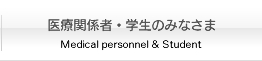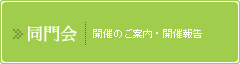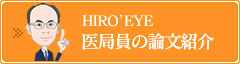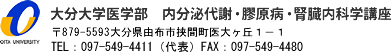ホーム > 教授ごあいさつ
教授ごあいさつ
 大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授 柴田洋孝
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授 柴田洋孝
この度、平成25年6月1日付けで大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授に就任いたしました。本講座は大分医科大学内科学第一講座として昭和53年に髙木良三郎教授(初代)により開講され、坂田利家教授(第二代)、吉松博信教授(第三代)にわたり着実に発展してまいりまして、私は第四代目です。
内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座は、平成25年の大分大学の講座再編により、総合内科学第一講座を引き継いで誕生し、内分泌糖尿病内科、膠原病内科、腎臓内科の3つの診療科を幅広く担当させていただきます。
大分と慶應義塾の縁は、福澤諭吉が幼少期を過ごした中津市があることがあげられます。私は医学部卒業後25年間を慶應義塾で過ごしてまいりましたが、慶應義塾で身につけた「慶應スピリッツ」を持って、学外の大分の地で指導力を発揮して新しい教室作りを目指してまいります。
私が目指す教室として臨床・研究・教育・地域医療の4つの柱を考えております。
- 3つの内科が連携した幅広い臨床力を発揮できる教室: 講座再編であらためて内分泌糖尿病内科、膠原病内科、腎臓内科の専門医およびその育成を行う教室として、各診療グループの垣根を越えた協力体制により、内分泌性高血圧症、糖尿病、慢性腎臓病、膠原病が様々に合併した多様な生活習慣病を、総合的な眼を持って診る医師の育成を目指します。
- リサーチマインドを持つ医師を育てる教室: 良い診療を行おうとする医師はリサーチマインドを持たなくてはなりません。最近の研修医制度の変革に伴い、リサーチマインドを持った若手医師が減っております。「実験」とは本来、何が起るかわからないからとりあえず試してみることで、大学のみで行うことができる貴重な活動です。ひとたび白衣を着て、日常と隔離された実験室に入ると、好奇心と冒険心が解き放たれ、水を得た魚のように打ち込む若手研究者を育成したいです。研究に対する若手の意識改革を行って、研究の楽しさを伝えてまいります。
- 魅力ある研修システムと教育体制:大分大学医学部は卒業生の約3割のみが大分大学での研修を行うのが現状であり、将来の大分県での医療を考えると、一人でも多くの医師が大学へ残ることを希望するような魅力的な教育体制を他の内科教室とも連携して作り上げてまいります。
- 大分県の地域医療に貢献できる教室: 大分県の特性として、人口10万人あたりの透析人口が全国第四位で、糖尿病、高血圧症、脳血管疾患なども全国第7位であり、生活習慣病や認知症の割合が極めて多いことが上げられます。大分県の地域性を考えて、一人でも多くの専門医(糖尿病、高血圧、内分泌代謝、腎臓、透析、リウマチ)を育てて、チーム医療を一緒に行っていく看護師(糖尿病療養指導士など)の育成も主体となり行っていきます。都市部の大学病院にはない「強い特徴」を出せるような診療、研究、教育を行って、存在意義を発信してまいります。
もとより身に余る重責ではございますが、内科学講座全体と連携して大分大学医学部および大分県の地域医療の発展に取り組む所存でございます。今後ともいっそうのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
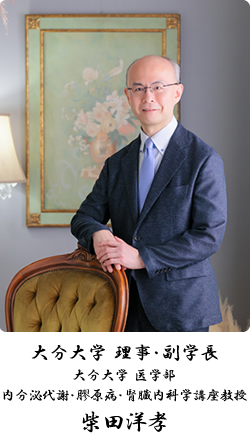
10th Anniversary~Aufschwung~
(10年の軌跡~飛翔~)
平成25年6月1日付けで本講座教授に着任して12年が経過しました。
本学の内科学講座の再編により、3診療科から構成される唯一の講座は、医局長、副医局長、3医長(病棟医長・外来医長・教育医長)をリーダーとするスタッフメンバーと医局員と秘書の皆さんの尽力、協力によって強靱でレジリエントな組織力が培われてきました。
また、大分県内において大分市、別府市に加えて、県北、県南の多くの関連施設において、内科部長と常勤医を派遣し大分県全体の地域医療に貢献しております。私が着任した2013年から2025年度までの入局者は85名にのぼり、内科学講座再編で一時減少した医局員、同門会員の数は元の人数を超える講座に進化してきました。
この12年間に講座から学内に4名の教授(加隈 哲也教授(医学部看護学科)、正木 孝幸教授(医学部看護学科)、後藤 孔郎教授(グローカル感染症研究センター)、中田 健教授(福祉健康科学部)を輩出することができました。
今年度は、医局長(福田 顕弘准教授)、副医局長(尾関 良則助教)・病棟医長(工藤 明子病院特任助教)、外来医長(尾崎 貴士助教)、教育医長(吉田 雄一講師)の体制で運営しています。作成が遅れていた10周年記念誌も「10th Anniversary~Aufschwung~(10年の軌跡~飛翔~)」のタイトルで作成しました。鈴木 美穂先生、後藤 孔郎先生、佐田 健太朗先生、梅木 達仁先生を中心にかなりの時間をかけてまとめてくださり感謝いたします。
私が着任してからの皆様の診療、教育、研究、地域医療などの多様な業績、活動を振り返ることにより、今後の10年、さらに長期の将来展望を考えたいと思います。
2026年は大分大学医学部創立50周年を迎え、私の専門分野の学会である日本内分泌学会創設100周年に当たります。その節目の年に、第22回国際内分泌学会議/第99回日本内分泌学会学術総会を京都で合同開催いたします(九州大学・小川 佳宏教授と共同会長)。
学会のテーマとしました「Enlightened Endocrinology in Unprecedented Times(異次元の時代における進化する内分泌学)」のように、我々の講座におきましても、医局員、同門会員の皆様とご一緒に変化の目まぐるしいこの異次元の時代を生き抜いて、さらに発展を遂げることができるように運営をしていきたいと考えております。
私事になりますが今年の10月1日付けで理事、副学長、研究マネジメント機構長を拝命し、大分大学全体の運営、特に研究関連の強化を担当することになりました。この12年間で講座の3つの診療科では信頼して任せられるスタッフが育っており、次世代を担うスタッフと一緒になって、我々の講座、そして内科学講座、医学部、さらには大分大学全体の次の10年間の発展、飛翔に向かって尽力していきたいと思います。
引き続き、皆さまとの絆を深めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
(令和7年10月1日)
講座のロゴ作成について
 私が本講座の教授として着任してちょうど3年が経過しました。
私が本講座の教授として着任してちょうど3年が経過しました。
我々の講座は、本学内科学講座の中で、内分泌糖尿病内科、膠原病内科、腎臓内科の3つの診療グループからなる唯一の講座です。今後はあらためてこの3つのグループの結束を強くして、診療、教育、研究にあたっていきたいと思っております。それにあたり、着任してだいぶ時間が経過してしまいましたが、あらためてスタッフで相談して、講座のロゴを作成し、私の本講座への強い思いをこめて考えました。
まず、「3本の矢」ともいえる3つの診療グループの特性を生かした垣根のない融合です。ロゴマークの円マークは3つのアームが手に手を取り合っています。その「3本の矢」のイニシャルは、「E (Endocrinology)」、「R (Rheumatology)」、「N (Nephrology)」であり、ロゴの中心にあります。
さらに、内分泌糖尿病内科が扱う代表的疾患である副腎疾患、腎臓内科が扱う腎臓のイラストに加えて、腎臓から出ている2本の尿管は膠原病で用いる抗体製剤の免疫グロブリン重鎖が融合したイラストを円の中に描き、副腎・腎臓・尿管からなるこのイラストは「M (Metabolism)」にも相当します。
そして、副腎からは3つのホルモンが殻を破って分泌され、世界の舞台に躍り出ることを願っているというメッセージをこめました。
私は、講座の3グループは各々独立した活動をしながらも、臨床カンファレンスやリサーチカンファレンスなど合同の活動も定期的に行うことで、様々な立場でものを考えることができ、多様な視点を持って深く考え、そして悩み、一見して正解がないような問題にも立ち向かうことができる医師を育成したいと考えております。今後、本ロゴマークはホームページをはじめとして、学会、研究会、講演などの発表スライド、ポスターなどにも多くの医局員の先生方に本学のロゴと並べて使っていただけますと幸いです。
平成28年6月13日 柴田洋孝